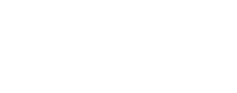ところで一般に「京焼」の名で呼ばれるやきものは、茶の湯の流行と普及を背景に江戸時代の初めごろから東山地域を中心として広がった京窯で焼かれたやきものをさしている。
桃山時代、長次郎のもとで始まった「楽焼」(聚楽焼)は、ふつう京焼のなかには含まない独立したやきものとして考えられている。
京焼の始まりについては、様々な説が伝えられているが、一説には室町時代宝徳年間(1449~52)に、小松谷清閑寺の職人であった音羽屋九郎右衛門が茶碗坂の窯跡を発見し、深草に窯を移して陶器を作ったとされている。
また永正年間(1504~21)には、渋谷の工人元吉が深草式の方法で京焼を改良し、釉薬による新しい工法を発明、その後清水に窯を移したという。
さらに桃山時代から江戸時代にかけた大正・慶長年間(1573~1615)になると、正意万右衛門、宗三、源介、源十郎といった陶工が現れ、音羽・清閑寺・小松谷・清水などの地で製陶を行った。
さて、京焼という言葉が初めて文献上にみられるのは、博多の豪商神谷宗湛の日記の慶長十年(1605)の条に記される「肩衝京ヤキ」があげられる。
この京ヤキが今日でいう京焼のことであるかどうかは明らかではないが、少なくとも桃山時代の慶長初年頃には、京都に窯業が始まっていたことがわかる。
また、江戸初期京窯の動向については、寛永から慶安年間(1624~52)の鹿苑寺(金閣寺)住職鳳林承章和尚の日記『隔冥記』に史料が多くみられる。
その日記によれば、粟田口を中心とする東山山麓や北山に本格的な陶窯が起こっており、粟田口焼、八坂焼、清水焼、音羽焼、御菩薩池焼、修学院焼などの名が見出される。
粟田口焼のはじまりは、寛永元年(1624)に瀬戸の焼物師三文字屋九右衛門が粟田口蹴上に窯を築き、数多くの茶器を焼いたのが最初である。その作品にはみな粟田の印が押されていた。
また五条坂清水焼の陶業のはじまりについては、一説には茶碗坂の音羽屋惣左衛門の九代目が衰微して、文政二年(1819)に大仏(方広寺)境内鐘鋳街の丸屋佐兵衛に窯が譲られ、その窯を自宅の裏に移したのが最初であるという。
他に慶長十八年(1613)に大仏の巨鐘鋳造の時、窯を五条坂に移したのが初めであるという説や、慶長の末に窯煙が阿弥陀ヶ峰の豊公廟をおおうので移転を命じられ、窯を五条坂に移したのが始まりだとする説がある。
政治・文化・経済の中心で育った背景のもとで都市生活の維持に必要な職種が必要であり、京焼も其の一端を担っていた。
着衣は室町、建築は飾り器具、食は食器、香道は香具、華道は花器、茶道は茶器等それぞれの数寄者の好みに応じて制作されて来た。
その場所は洛内各地であり、京焼の一番多く生産されたのは東山地域を中心としていた。